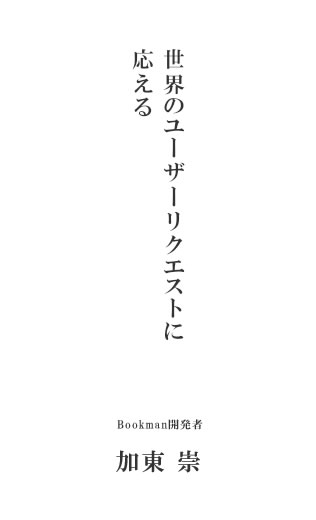限られた環境の中で最高のパフォーマンスを
――そうなってくると、バックグラウンドでの処理がかなり複雑になってくると思うんですが、そこもマルチスレッドの方式でされているんですか?
加東崇氏: そこも運良く、僕がゲーム業界でやっていた時というのは、PS3やXbox360など、CPUがマルチコア化されてきた時代なんです。そのマルチコア化したものに対して最大限の性能を発揮させるには、全部のコアをうまく使い切るというノウハウが必要でした。ゲーム業界にいる時に、そういう考え方ややり方には慣れていたので、「いつもの仕事」という感覚で、それをそのまま応用しました。
ただ僕はその時にはiPadでアプリを作るという経験がなかった。だからユーザーインターフェースの方はすごく苦手な分野でした。最初のバージョンは、いわゆるiPhone、iPadでよく見るようなアプリのデザインではなく、本当に独自の、良くないデザインで作っていました。ですから、苦手な部分は作り始めてからユーザーのご意見やご要望を聞いて、学びながら、苦労しながらどんどん改善していきました。

――Bookmanは早いだけではなく、動作が気持ちよくできていますね。
加東崇氏: ウェブ上のインターフェースは、パソコン上で動くので環境がばらばらなので、スムーズには動かしづらいというのがありますが、ハードウエアがiPhoneやiPadのように、ある程度固定される環境だと開発側としては、調節はしやすいです。逆にAndroidだと難しそうだとは思います。
――Bookmanはかなりオリジナルに作り込まれているという印象を受けました。
加東崇氏: そうですね、とにかく高速にめくれるというのが、最初特徴になっていたので、それを突き詰めて、実際の本みたいに読めるようにしたいと思ったんです。実際の本を読む時には、バラバラめくるじゃないですか。雑誌とかの場合、そういうようなこともしたいなと思うと、1ページ1ページスライドしていると大変なので、本みたいに一気にバラバラっとめくれたり、1ページずつでもめくれたり、両方対応できるようにと考えて、今のような状態になりました。
――読むだけではなく、メモができる機能などが少しずつ拡張されていますね。
加東崇氏: そうですね。僕は、英語の勉強を今でもずっとやっていますが、英語の文章を読んでいてわからない単語があった時、その時点で1回調べて覚えますが、ページが進んでいくと忘れてしまうことがあります。その経験を踏まえて、iPadで読む時はせっかく色々と電子的なことができますから、1回書き込みやマークをしたら、そのページにいつでも簡単に戻ってこられるようにしたいと思ったんです。今iPad版では、タグテーションをつけたページにボタン1つでポンポン飛んで行ける機能があります。これは、特に学習する時には便利な機能になっています。1回読み終わった後に「復習しよう」と思ったら、最初のページからそのタグテーションしたページだけを順番にどんどんページを飛ばして読んでいけるんですね。これは僕が個人的に気に入っている部分です。
――なるほど。3D系のプログラマーの方は、こういったパフォーマンスが出るようなアプリケーションが得意なのですね。
加東崇氏: そうですね、そういう部分には結構こだわります。エンジニアとしても、この限られた環境の中でどこまで最高のパフォーマンスを出せるかというのは、すごくやりがいのある部分です(笑)。
『ポケコン』との出会い
――iOS以外でも個人として、プログラムを公開されたことはあるんですか?
加東崇氏: ツールのアプリは、学生の時に3Dのデモプログラムを公開していました。その時はXboxの1が出ていた頃です。それに相当するグラフィックスのビデオカードがあって、それをパソコンに差して、限界まで突き詰めて「ここまで出せたぞ」っていうのを自慢したりすることが好きでした。もともと学生の時もずっと3DCGのレンダリングに特化してやっていたので、ツール作りとかはあまりやっていませんでした。
大学は経営情報学部で、経営情報の「経営」の方には興味が全然なかったのですが、「情報」の方でプログラミングの授業がありました。3Dに関しては独学で、自分で作ったアプリケーションとかを先生に見せて、僕から先生に説明するという感じでした。プログラムは高校生の時から興味を持ち始めて、BASICとかC言語を使えるようになっていました。
僕が高校生の時に、友達がプログラミングの本に載っていた小さなプログラムのゲームのコードを全部入力したものが、ポケットコンピュータ(プログラムを自分達で書くことによって様々な動きをさせることができるようになっている機械)で動くのを見せてもらった時に「何だこれ、すごい」と衝撃を受けて、自分も作り始めました。「こんな面白いものがあるんだ」と、どんどん好きになって、独学で研究を進めていったんです。
――では、そのお友達が最初にプログラムに関心があったんですね。
加東崇氏: そうですね。その人に最初は教わったりしました。最初は画面で右ボタンを押したらアスキー文字が出るとか、そういう基本的なところから始まって、それ自体がすごく楽しかったですね。だからミニゲームを作って友達に遊んでもらうっていうのがとても楽しくて、それでプログラミングを勉強していって、結果ゲーム業界に入ったという流れです。僕の高校の時は、パソコンっていうとPC98とかPC‐9821とか、画面が256色とかそういう時代です(笑)。その時はパソコンもすごく高かったので「買って」って言っても買ってもらえなかったし、初めてのPCがPC‐9821でした。
――その時代から、BASICでそこから3Dに行かれるというのは、いばらの道ですね。

加東崇氏: BASICって、絵を表示するとかの簡単なコマンドが最初から用意されているんですよ。だから絵を出すというのはすごく簡単で、最初は2Dのゲームをちょこちょこやっていましたが、時代の流れは3Dになってきていました。プレステやセガサターンは、僕が高校の時に発売されたので、ちょうどその流れに合わせて雑誌とかでも3Dの話題が色々出てきていて、そういうものを見ながら勉強して、自然の流れで3Dになっていきましたね。そこからiOSにつながるんです(笑)。
僕はずっとゲームをやっていたのに何でいきなり電子書籍リーダーなのかというと、単純にiPadっていう新しいデバイスにすごく興味があったのと、もともと何かを作って誰かが喜んでくれるというのがすごくうれしくてプログラマーになったという経緯があったので、そこは全く変わらずに共通しているんです。Bookmanを作って人に見せたら友達が喜んでくれて、自分の奥さんとかも喜んで、「じゃあ使うよ」って言ってくれて、まずは身近な人達のために色々機能をつけましたし、色々なユーザーの方々から要望を頂いたら、そういう方々を喜ばせたいから機能を付け加えていったりしたんです。
どの国の人にも、シンプルかつ快適にストレスなく
――Bookmanに色々機能がありますが、何かこだわりのようなものがあればお聞かせいただけますか?
加東崇氏: スキャンしたPDFを快適に読めることが優先順位としては第1です。こだわっていたのは、あまりごちゃごちゃした機能は入れずシンプルな状態を保ちつつ、一目見て使い方がわかるということを意識しました。シンプルかつ快適にストレスなくということです。
――Bookmanはアイコンや色々なUIの工夫によって、アイコンで直感的にわかるようになっていますが、その辺も試行錯誤されましたか?
加東崇氏: そうですね。最初のバージョンは英語版で出していました。App Storeに出すということは世界に公開するということですし、その時自分がアメリカにいたということもあって、最初から世界の人達をターゲットにすることは意識していました。実は英語がそんなに得意ではないので、細かな文章で説明することは苦手なんですよ。だからアイコンプラスちょっとしたシンプルな一文で伝わるようなことを意識していました。そして、できるだけ日本固有の機能などは入れないようにしました。例えば日本とアメリカとの違いでいうと、縦書き横書きがあるので、ページをめくる方向を変えたりすることが必要になりますが、これは基本的に全部オプションで選択できるようにして、「どの国の人でも使えるように」ということを意識して作っています。
著書一覧『 加東崇 』